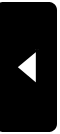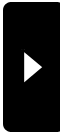2016年11月24日
顎関節症になりました!
顎関節症になってしまいました。
以前から左の顎関節に違和感があったのですが、
数日前から食事の時に、顎関節がガクッとなって
痛みが出るようになりました。
咀嚼の度ではないのですが、動きが止まる程に
痛みが強いので、真剣に治療する事にしました。
顎関節の直上と下顎の圧痛点の2か所にお灸をして
その後、顎関節の矯正と運動療法です。
4回程の治療で、食事の際の激痛が無くなりました。
私が患者さんに治療する場合は、
鍼と運動法の指導がメインの治療です。
今回は、自分では顔に鍼が出来ない為に、
家人にお灸をしてもらったのですが、
顔のお灸に抵抗のない方であれば、
顎関節症へのお灸の効果は、かなり良いと感じました。
2016年10月21日
足首の捻挫 スポーツへの復帰
バスケットボールやバレーボール、サッカー、柔道など
体育会系の学生は、よく足首の捻挫をします。
腫れや痛みが強い時には、冷やして、
固定して安静にすることが一番です。
整形外科や整骨院で診てもらって、スポーツなど
練習を休む必要があれば、休まなければいけません。
その方が早くスポーツ復帰できて、問題が残る事も
少ないものです。
足関節の捻挫で靭帯をひどく炒めると、
足関節が緩くなります。
足を内反(足裏を見るように足を捻った状態)させると
怪我をしていない方と比べて、内反の程度が強くなって
いれば、靭帯が緩んでしまった可能性があります。
スポーツ復帰の際は、医療機関と相談して
必要に応じてテーピングやメディリップでの固定など
必要な手当てをしてください。
自分の判断で行わないで、担当の先生と相談しながら
徐々にスポーツに復帰していく事が大切です。
緩んだ靭帯はほとんど元に戻らないものです。
そうした場合は、筋肉の強化を行う事で対応できます。
日常生活には支障が無くても、緩い足首は運動能力を
下げて、怪我の原因にもなります。
しっかりと、足首周辺の筋肉を鍛えておく必要があります。
学生のスポーツ障害は、花音堂では復帰まで
細かく対応しています。気軽に相談して下さい。
2016年09月28日
足首の捻挫
足関節(足首)の捻挫は日常的に良く起こるものです。
特に、内返し(足裏を内側に向けるような動き)による
足関節の靭帯損傷が起こりやすいです。
これは、関節の構造上、内返しになりやすい事と
外側の靭帯は内側の靭帯よりも弱い事も一因です。
中学生、高校生のサッカー部やバスケ部などの運動部や
社会人でも、野球やバレーなどを趣味でやっている人も
よく足関節を痛める事があります。
また、普通に歩いていても、路上の段差で
捻挫を起こす事もあります。
怪我をしたら、すぐに近くの整形や整骨院にいく事を
お勧めします。
痛みが強かったり腫れがひどい時には、靭帯などの
軟部組織に相応の損傷が考えられます。
早い時期に、固定や冷却などの処置を行う事が大切です。
整形外科や整骨院などの医療機関にかかるようにしましょう。
怪我から日常生活が元通り行えるまで、診てもらう事で
早期治癒と、痛みや動きの制限などの症状が
残ることを防止できます。
特に、スポーツをやっている方は、スポーツの復帰に
ついて、相談しながら無理なく行う事が大切です。
今は多くの整骨院でテーピングをしています。
スポーツをやる方は教えてもらって、
足関節のテーピングは自分で
出来る様にすることも何かと便利です。
2016年09月15日
自律神経失調症と鍼治療
自律神経というのは身体の中で、内臓や血管・眼球・内分泌等を自動的にコントロールしています。自律神経には、交感神経と副交感神経の2つがあり、おのおの対立した働きをしています。例えば、人がケンカをしているような時には交感神経優位、家で寛いでいる時には副交感神経優位になります。状況に応じて、その時その時に必要な身体の状態を自動的に作り出すのが自律神経です。普段はバランスよく身体を調整しているのですが、仕事や人間関係・病気などでストレスが続いたりすると、自律神経のバランスが崩れて、
血圧や内臓の働きに不具合が起きてきます。頭がカーッそして来る逆上せや、足の冷え、胃腸の不調、不眠、など人により多彩な症状を示します。鍼灸治療では、本人の訴えている症状に対しての治療はもちろん、自律神経のバランスを取る事ようなツボを使う事で、安定した自律神経を取り戻すことが可能です。表に出ている症状だけでなく、患者さんそのものを整えていくという東洋医学の方法が効果を上げる事が多いものです。
2016年09月01日
2016年05月14日
寝違い
朝起きると頸が痛く、左右に動かしたり上を向いたりできない、
という事は割と多くの方が経験している事と思います。
いわゆる寝違いです。
睡眠中の不自然な姿勢や冷えや過労などが原因で
痛みが起こるものです。症状が強いと本当に頸が回らない、という
状態になります。本人も大変不自由です。場合によっては、
車の運転などに支障も出てきます。
寝違いは鍼治療にとっては、得意分野の一つです。
中国では寝違いの事を「落枕」と言います。
手の甲には寝違いに使うツボがあり、それも落枕と言います。
先日も30代男性の方が寝違いで来院しました。
頸に痛みがあり、横を向く動きが半分くらいに制限されていました。
まず、落枕のツボと、他にいくつか手にあるツボに鍼をしました。
その後は、実際に痛みのある頸周囲を丁寧に触診して、
痛みのある部位、筋肉が固くなっている部位、主要なツボに鍼をしました。
こうした治療で、寝違いは驚く程良くなりました。
寝違いは早いうちに治療すれば、治りも良いものです。
お気軽に相談ください。
2016年04月24日
脊柱管狭窄症の治療
背骨は椎骨という骨が積木を積重ねたようになって出来ています。
椎骨には後ろに椎弓と呼ばれる部分があります。
この椎弓はリング状になっています。
このリング状の物が積重なって管を作ります。これが脊柱管です。
脊柱管の中には、脊髄や馬尾という神経が通っています。
通常、脊柱管は脊髄等が収まるのに十分なスペースがあります。
しかし、ヘルニアや加齢変化で脊柱管が狭くなることがあります。
そうすると、脊髄や脊髄から出て足などに行く神経根に触って
刺激を与えます。その刺激する部位によって、
脚や腰に痛みや痺れ筋力低下等の様々な症状が出てきます。
脊柱管狭窄症は基本的には手術をしなければ治りません。
神経の圧迫が強く、歩行障害や激烈な痛みがあれば、
病院では手術を勧めます。しかし、そこまで行かない方は、
日々不快感や痛みに耐えて生活しているかと思います。
鍼灸治療は脊柱管狭窄症そのものを治すものではありません。
しかし、症状を改善する事は可能です。
症状が出てからどの程度の期間経過しているか。
日常生活への支障がどの程度か、等により効果が
出るまでの期間や効果の程度に差はあります。
数年間、歩行に支障があり、「間歇性跛行」といって、
数分あるいは100メートル程歩くと足腰が痛くなり、
暫く休むとまたあるけるようになる・・・と
いう症状がある患者さんがいました。この方は84才女性です。
週に1回程お灸と鍼による治療を続けた所、
間歇性跛行が改善しました。
この方は、今は朝のウォーキングを行っています。
最近も89歳の女性が治療に来ました。
この方は、間歇性跛行は無く、
左右下肢の痺れと痛みが症状でした。
3回程の鍼で症状は、あまり気にならない程度まで改善しました。
寒い時期に症状が悪化せずに良くなるのは、良い事です。
脊柱管狭窄症で、病院での治療をあまりなさっていない方は、
鍼灸治療も1つの選択肢として有効です。鍼をする部位は、
と下肢・足趾等です。ぜひお試しください。
2015年03月06日
御灸で胃 すっきり
胃の不調で、日々の食事が美味しく摂れないのは辛い事です。
そうした胃の症状に対しても、鍼灸は効果的です。昔から「胃の六つ灸」と言って、背中に左右対称に6つのツボを使って治療する事が行われています。これは胃の症状に限らず、消化器の 食べ過ぎ飲み過ぎ、ストレス等、胃の調子はちょっとした事で悪くなります。
症状全般に効果的です。治療中・治療後に、背部に心地良い温感があるので、治療自体も快適な事が特徴です。
胃炎で内服薬を服用している患者さんが来院した事がありました。週に1、2回のお灸で数週間で症状が軽くなりました。この方には不眠症もありましたが、お灸の良い副作用で、睡眠も改善したとの事でした。不眠は不眠の為の治療があるのですが、背中のコリもとれて、血行が良くなった事で思わぬおまけが付いてきたようでした。
2015年02月11日
今、お灸が人気
お灸というと、ちょっと古臭いし、熱くて怖い、と思う方も多いかと思います。ところが、今ちょっとお灸が人気なようです。
お灸にも色々あります。大豆くらいの大きさのお灸を最後まで燃やすような恐ろしい灸もありますが、今は、まずそうしたお灸はありません。温灸といって、肌に直接火が当たらないお灸もあります。これは千年灸やカマヤ等の商品で一般に販売されているので、ご存知の方もいるかもしれません。温灸は一般の方が家庭でも出来て暖かく気持ちがいいものですが、ピンポイントでツボ治療が出来るものではありません。
鍼灸院で広く行われているのは、透熱灸というお灸です。多くは半米粒大といって、お米の半分ほどの大きさの艾を使います。当院で行っているお灸はこの半米粒大のお灸を使います。また、
八分灸と言って、お灸の火が皮膚に届いた瞬間に、上から指で押して火を消します。そうすると一瞬熱感がツンときてそれで終わりです。熱い感じを我慢するという事は無く、軽くちくっとする感じです。やけどの心配もありません。皮膚に熱が染み込むような感じがあればツボ治療の効果がありますので、適切なツボを選んで、タイミングを計って八分灸を行えば、気持ち良く効果のあるお灸治療が出来ます。
お灸は小さなんのですが、ポカポカ感が長続きして、寒い時期にはとても良いものです。
冷え症やおなかの調子が悪い時、痔の治療にもお灸は効果的です。鍼が好きでない方が、お灸を使って体調調節をしたり、自律神経失調症の治療をする事もあります。また、昔から逆子のお灸が有名で治療効果も高いものです。
この寒い時期にはぜひともお勧めなのが、お灸です。
2015年02月02日
こむら返りを治そう
ふくらはぎが突然つっぱって痛くなることがあります。ふくらはぎ痙攣、こむら返りです。
数分我慢していれば、いずれ治まってきますが、その痛みはきりきりとかなり辛いものがあります。若い方でも、夏に海やプールなどへ行って、ウォーミングアップなしで泳ぎ始めると起こる事があります。高齢者の方は、夜間に寝ている間に、痛みで目が覚めて辛い思いをする方も多いようです。
こむら返りの原因はいくつかありますが、多いものが、冷えと筋疲労です。普段身体を動かさない方が、久しぶりに運動したりしますと、運動中に起こる事もありますし、その夜に起こる事もあります。寒い日に、掃除などしていて不自然な格好で足に力を入れた時に、突然起こる事もあります。1度こむら返りが起こると、同じ部位で頻繁に起こるようになる事もあります。
治療には漢方薬や鍼灸などもありますが、誰でも出来るのがストレッチです。そうは言っても、ストレッチも適切な方法を取らないと効果的ではありません。
まず、ストレッチをしようとする脚を伸ばして座ります。反対の足は胡坐のような形で曲げておきます。伸ばした方の脚の膝は伸びているのですが、痛みや膝の変形などで完全に伸ばせない時には、二つ折りにした座布団などをひざ下に入れておきます。この状態で足が垂直に立つようにします。足を立てられない時には、出来るだけ立てるようにします。そうして両手で爪先全体をつかむようにして、足を反らせるようにします。手が届かない時には、両手にタオルを持って、タオルを使って足を引くようにします。この時注意するのは・・・。
●膝を曲げない事。
●力ずくでやらず、ゆっくり痛む筋肉をなだめるように引いていく事。
●足を反らす時、ふくらはぎのがゆっくりと伸びていく感覚を確認しつつ行う事
●30秒~1分程かけて行う事。それを数回繰り返す事。
●呼吸は止めないで、息をゆっくり吐きながら行う事
注意点は一般的なストレッチと同じなのですが、違うのは固く収縮している筋肉を伸ばさなければいけない事です。慌てて無理に行うと筋繊維を痛めたり、伸ばそうと思っている場所が伸びない事になります。
普段から、お風呂上りや眠る前にストレッチの習慣をつけておくと予防になります。
ご自分でストレッチをするのが面倒な方や、ストレッチの方法を詳しく知りたい方は、お近くの整骨院や鍼灸院で対応して頂けると思います。
時には、病気の症状として、こむら返りが起こる事もありますので、頻繁に起こる方で内科的な不調のある方は、医師にご相談ください。

数分我慢していれば、いずれ治まってきますが、その痛みはきりきりとかなり辛いものがあります。若い方でも、夏に海やプールなどへ行って、ウォーミングアップなしで泳ぎ始めると起こる事があります。高齢者の方は、夜間に寝ている間に、痛みで目が覚めて辛い思いをする方も多いようです。
こむら返りの原因はいくつかありますが、多いものが、冷えと筋疲労です。普段身体を動かさない方が、久しぶりに運動したりしますと、運動中に起こる事もありますし、その夜に起こる事もあります。寒い日に、掃除などしていて不自然な格好で足に力を入れた時に、突然起こる事もあります。1度こむら返りが起こると、同じ部位で頻繁に起こるようになる事もあります。
治療には漢方薬や鍼灸などもありますが、誰でも出来るのがストレッチです。そうは言っても、ストレッチも適切な方法を取らないと効果的ではありません。
まず、ストレッチをしようとする脚を伸ばして座ります。反対の足は胡坐のような形で曲げておきます。伸ばした方の脚の膝は伸びているのですが、痛みや膝の変形などで完全に伸ばせない時には、二つ折りにした座布団などをひざ下に入れておきます。この状態で足が垂直に立つようにします。足を立てられない時には、出来るだけ立てるようにします。そうして両手で爪先全体をつかむようにして、足を反らせるようにします。手が届かない時には、両手にタオルを持って、タオルを使って足を引くようにします。この時注意するのは・・・。
●膝を曲げない事。
●力ずくでやらず、ゆっくり痛む筋肉をなだめるように引いていく事。
●足を反らす時、ふくらはぎのがゆっくりと伸びていく感覚を確認しつつ行う事
●30秒~1分程かけて行う事。それを数回繰り返す事。
●呼吸は止めないで、息をゆっくり吐きながら行う事
注意点は一般的なストレッチと同じなのですが、違うのは固く収縮している筋肉を伸ばさなければいけない事です。慌てて無理に行うと筋繊維を痛めたり、伸ばそうと思っている場所が伸びない事になります。
普段から、お風呂上りや眠る前にストレッチの習慣をつけておくと予防になります。
ご自分でストレッチをするのが面倒な方や、ストレッチの方法を詳しく知りたい方は、お近くの整骨院や鍼灸院で対応して頂けると思います。
時には、病気の症状として、こむら返りが起こる事もありますので、頻繁に起こる方で内科的な不調のある方は、医師にご相談ください。